ESG 視点での「よきモノづくり」を基軸に、グローバル・シャープトップ企業への変革を加速している花王株式会社。そのために重要な役割を担っているのが、全社グローバル規模で進めている DX への取り組みです。まずは、デジタル人財を育成するため、グローバル全社員を対象にした教育プログラムをスタート。さらに生成 AI を活用したデータ基盤拡充の両面から取り組みを推進しています。
社内で使う生成 AI としては、Azure OpenAI Service をベースにした「Kao AI Tools」や、Microsoft Copilot などを提供。またデータ基盤としては、各種マイクロソフト製品を活用した「Kao i-Lake」を提供しています。
このような取り組みよって、DX 人財の数は急速に増えつつあり、データの民主化も進んでいます。今後はこの Kao i-Lake に Microsoft Fabric を導入することも検討。全社員がデータと AI を使いこなしながら、ビジネスや顧客体験の革新を持続的に行える企業になることを目指しています。













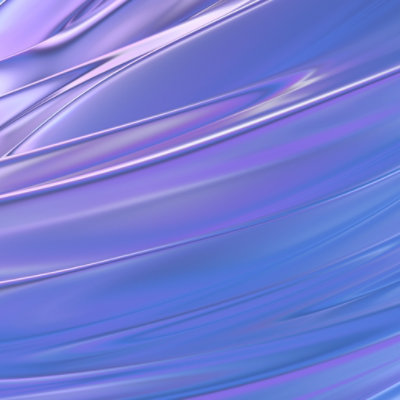




Microsoft をフォロー